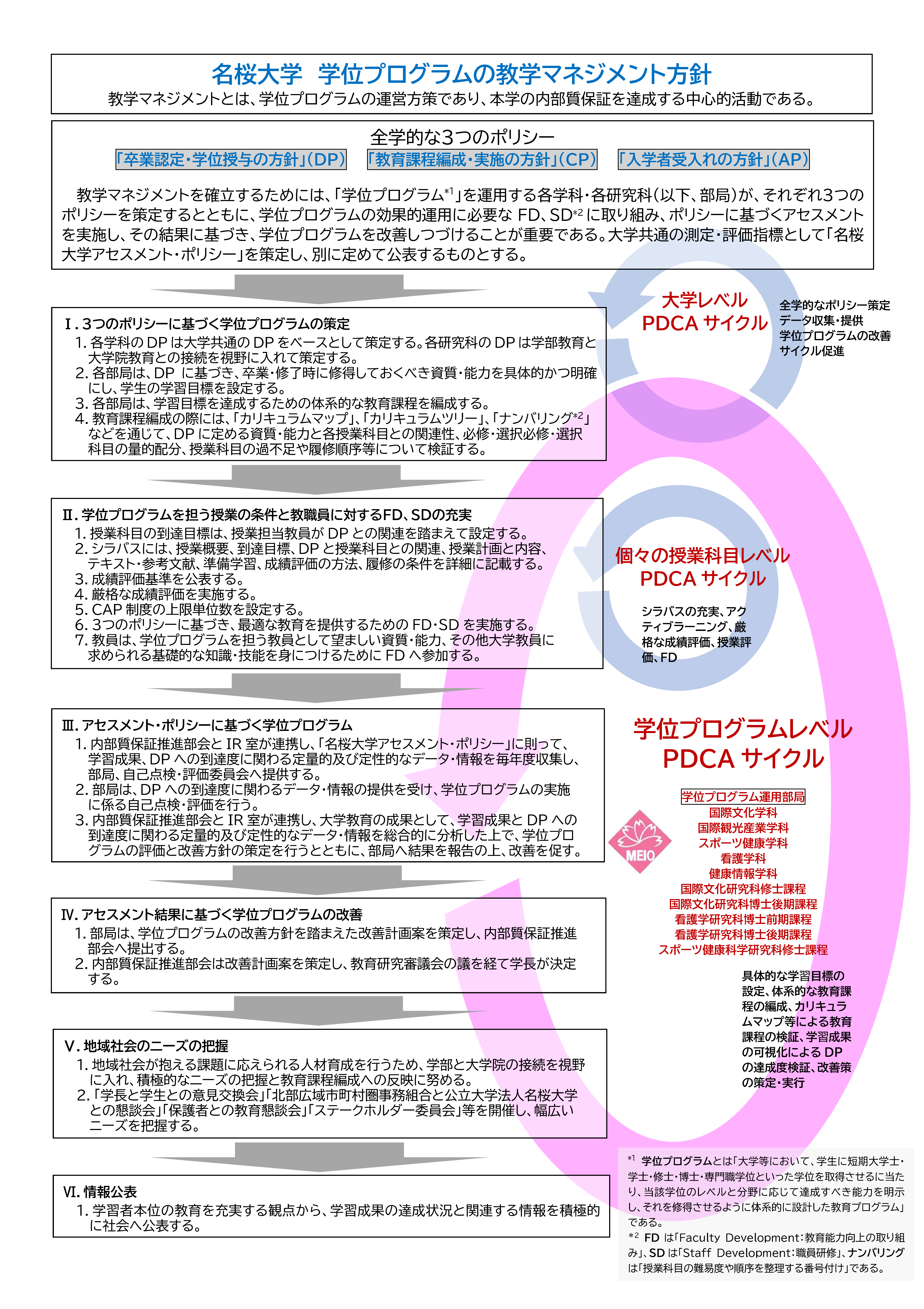名桜大学 学位プログラムの教学マネジメント方針について大学紹介
大学紹介
教学マネジメントとは、学位プログラム※₁の運営方策であり、本学の内部質保証を達成する中心的活動である。教学マネジメントを確立するためには、学位プログラムを運用する各学科・各研究科(以下、「部局」という。)が、「卒業認定・学位授与の方針」(以下「DP」という。)、「教育課程編成・実施の方針」(以下「CP」という。)及び「入学者受入れの方針」(以下「AP」という。)からなる3つのポリシーを策定するとともに、学位プログラムの効果的運用に必要なFD、SD※₂に取り組み、ポリシーに基づくアセスメントを実施、そのアセスメント結果に基づき、部局長だけでなく教育活動に携わる全員が、学位プログラムを改善しつづけることが重要となる。
Ⅰ.3つのポリシーに基づく学位プログラムの策定
本学では、部局のDP、CP及びAPからなる3つのポリシーを定めた上で、学位プログラムを策定する。その際、学部教育のDPは大学共通のDPをベースとして策定し、大学院教育のDPは学部教育と大学院教育との接続を視野に入れて策定するものとする。
部局は、学位プログラムを効果的に運用するために、それぞれのDPに基づき、学生の学習目標を設定することで、卒業・修了時に修得しておくべき資質・能力として、具体的かつ明確に設定するものとする。 部局は、DPに定める資質・能力の育成に必要な授業科目をCPに基づき開設し、体系的な教育課程を編成するものとする。
部局は、教育課程編成の際には、「カリキュラムマップ」、「カリキュラムツリー」、「ナンバリング※₂」などを通じて、DPに定める資質・能力と各授業科目との関連性、必修・選択必修・選択科目の量的配分、授業科目の過不足や履修順序等について検証する。
本学は、学位プログラムの成果を大学教育の成果として点検し、評価するため、大学共通の測定・評価指標として「名桜大学アセスメント・ポリシー」を策定し、別に定めて公表するものとする。
Ⅱ.学位プログラムを担う授業の条件と教職員に対するFD、SDの充実
授業科目の到達目標は、授業担当教員がDPとの関連を踏まえて設定するものとする。 授業科目のシラバスには、授業の概要、到達目標、DPと授業科目との関連、授業計画と内容、テキスト・参考文献、準備学習、成績評価の方法、履修の条件等を詳細に記載する必要がある。その際、教養教育科目においては、大学共通のDPと授業科目との関連に加え、科目区分の教育目標との関連を明示することとする。また、複数の学位プログラムに提供される専門教育科目においては、学位プログラム別にDPと授業科目との関連を明示することとする。
本学は、成績評価に関する大学としての考え方を内外に示し、大学全体で厳格な成績評価を行うために、全学的な成績評価基準を策定し、公表するものとする。 各授業では、到達目標に応じた適切な成績評価手法が選択され、厳格な成績評価が実施されることが求められる。
本学は、1単位あたりの学習時間を確保する上で、CAP制度の上限単位数について、適切に設定する。
本学は、3つのポリシーに基づき、最適な教育を提供するためのFD・SDを、定期的に企画し、実施するものとする。
DPに則した最適な教育を提供するためには、授業担当教員がDPと各授業科目との関係を理解すること、そして学位プログラムを担う教員として望ましい資質・能力(専門的知識・技術等の教授技法)、その他大学教員に求められる基礎的な知識・技能(履修指導、進路指導、研究指導、アクティブラーニング、オフィスアワーの活用、シラバス作成、グループ指導、学習評価、障がい学生支援、ハラスメント予防、IRデータ活用力等)を身につけるためにFDに参加することが必要である。
Ⅲ.アセスメントポリシーに基づく学位プログラム
内部質保証推進部会とIR室が連携し、「名桜大学アセスメント・ポリシー」に則って、学習成果、DPへの到達度に関わる定量的及び定性的なデータ・情報を毎年度収集し、部局、自己点検・評価委員会へ提供するものとする。
部局は、DPへの到達度に関わるデータ・情報の提供を受け、学位プログラムの実施に係る自己点検・評価を行うものとする。
内部質保証推進部会とIR室が連携し、大学教育の成果として、学習成果とDPへの到達度に関わる定量的及び定性的なデータ・情報を総合的に分析した上で、学位プログラムの評価と改善方針の策定を行うとともに、部局へ結果を報告の上、改善を促すものとする。
Ⅳ.アセスメント結果に基づく学位プログラムの改善
部局は、学位プログラムの改善方針を踏まえた改善計画案を策定し、内部質保証推進部会へ提出するものとする。
内部質保証推進部会は改善計画案を策定し、教育研究審議会の議を経て学長が決定するものとする。
Ⅴ.地域社会のニーズの把握
地域社会が抱える課題に応えられる人材育成を行うことは、地域貢献を担う公立大学にとって重要な役割である。そのため、学部教育と大学院教育の接続を視野に入れ、積極的なニーズの把握と教育課程編成への反映に努めるものとする。
その際、「学長と学生との意見交換会」「北部広域市町村圏事務組合と公立大学法人名桜大学との懇談会」「保護者との教育懇談会」「ステークホルダー委員会」等を開催し、幅広いニーズを把握する。
Ⅵ.情報公表
学習者本位の教育を充実する観点から、学習成果の達成状況と関連する情報を積極的に社会へ公表するものとする。
※₁ 学位プログラムとは「大学等において、学生に短期大学士・学士・修士・博士・専門職学位といった学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を明示し、それを修得させるように体系的に設計した教育プログラム」である。
中央教育審議会(2009)『学位プログラムを中心とした大学制度の再構成について』(平成21年1月22日第74回大学分科会配布資料)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/siryo/attach/1259115.htm
※₂ FDは「Faculty Development:教育能力向上の取り組み」、SDは「Staff Development:職員研修」、ナンバリングは「授業科目の難易度や順序を整理する番号付け」である。
大学公式SNS